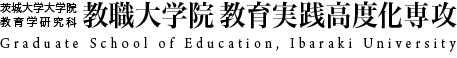授業の特徴
教職大学院の授業の特徴
コース間融合科目の新設
本学教職大学院における専門科目と実習科目では、専門性の異なる学生が協働して問題解決に取り組むコース間融合科目やコース間融合実習を設定しています。このような”融合”の科目を設定することで、個人が有している専門性に閉じることなく、同僚と協働し、地域や保護者と連携し、その専門性を学校や地域、そして社会に存在している様々な課題の解決に活用できる力が身に付くことが期待できます。
コース間融合科目(専門科目)の例
●社会の数理
「社会の数理」は社会的事象を数学の知識を活かして理解を深めていく授業です。授業では検地に活用する用具の製作に技術科の活動も取り入れて、「近世の検地」を実践します。
このように1つの教科にとらわれずに、教科・分野を横断した広い視野が身に付くようになります。
●子ども理解と学習支援
教育方法開発コースと児童生徒支援コースの学生・教員が1つの教材や事例を、教育学的視点および心理学的視点からとらえ、それぞれの物の見方、解決までの思考の仕方を学びます。これによって、多角的に教育現象を捉え、複数の解決策を想定できる教員を養成します。
コース間融合科目(実習科目)の例
●教材開発実習IB(教科領域、特別支援科学、養護科学の融合科目)
「教材開発実習IB」は、地域の社会教育施設(歴史館、水族館など)において、施設の特性を活かした子ども向けの教育普及活動に参画し、イベントの企画・運営、実践補助に関する活動を実施します。
本実習をとおして、教科・分野横断的な幅広い視野に基づいた教材開発力や、特別な支援を必要とする子どもへの教材開発力を身に付けます。
●課題発見実習(学校運営、教育方法開発、児童生徒支援の融合科目)
附属学校園の観察及び実践補助を行い、児童生徒の発達・学校種に即した学習内容や教育活動の全体像を把握し、学校運営の課題とともに、教師の指導の在り方を多面的に学びます。本実習をとおして、福広い視野から学校や自身の課題を明確化します。
校内研修の企画実践力のある教員
学校の課題をとらえ解決する手段として校内研修を企画し活用できる教員を育てます。そのために「校内研修の企画・立案と実践」及び「教育測定(評価)と校内研修」の科目を設定し、校内研修を通して他の教員とともに課題解決の糸口をさぐれるリーダーを養成します。
少人数での授業
専門科目の授業は、少人数で行われるものが数多くあります。授業の題材は、具体的なものばかりのため、様々な意見を出しやすく、討論も盛んに行われます。ほかの人の意見を聞くことで、自分にはない観点に触れることになります。
実務家教員と研究者教員のTTによる授業
これまでの修士課程と違い、研究者教員と実務家教員のTT(ティーム・ティーチング)によってすすめられる授業もあります。
実務家教員とは、長年、学校で教鞭をとってきた経験豊富なベテラン教員です。一つのトピックに対して、研究者教員の理論的な観点と、実務家教員の実践的な観点の両方の観点を取り入れた授業となります。
現職派遣教員と学部新卒者による協働の学び
教職大学院には、現職派遣教員が数多く学んでいます。現職としての経験を10年以上、多い人は20年以上もの経験を有しているベテランの先生たちで、学校で起こる様々な出来事に対する豊かな実践知を備えている先生が多いです。この現職派遣教員と学部新卒者とが一堂に集まって行われる授業もあリます。学部新卒者にとっては自分の不安や分からないことを現職派遣教員に相談できたり、同じ課題に対する現職ならではの見方を教えてもらったりすることによって、具体的で実践的な学びが促進されることを期待できます。現職教員にとっては、学部新卒者と話をすることで、若手の情熱や純粋な気持ちにふれて、自分を振り返ることが多いようです。
新しい修了のかたち
教職大学院では修士論文を書くことは必須の条件ではありません。教職大学院は高度な実践力をもった教員を育成することを目的にしていますので、修士論文という形ではなく、専門的な学びを実習とリンクさせながら問題解決の力を身に付けます。その方法は、自分が教員として必要だと思う力量を、現場での実習で実践することでも得られますし、実習を通して感じた疑問を調査や実験等の研究的視点をもって解決策を考えることもできます。
その研究成果は、実践研究報告書としてまとめ、研究報告会において発表していきます。様々な立場の先生たちから意見や感想を寄せてもらえるので自分の実践・研究を多角的にとらえる機会となります。
茨城県教育委員会、茨城県教育研修センターとの協力状況について
教職大学院は茨城県教育委員会や茨城県教育研修センターと連携し、「教育課程連携協議会」等において、教育委員会や近隣市町村の教育長と意見交換を行うなど、常に授業改善とカリキュラム改革を進めています。
そして、養成と研修の一体化の理念のもと、教育研修センターの指導主事・主査による教職大学院の科目への連携授業を実施して、県の最新の取り組みを紹介するなど幅広い大学院の授業を展開しています。
また、大学院生による教員養成セミナーへの協力、NITS・教職大学院等コラボ研修プログラム支援事業、茨城県教育研修センター「校内研修支援事業」への参画、教育研修センターでの研究成果発表会などを実施し、多様な授業外活動にも力を入れています。各事業の内容や様子は「お知らせ」をご覧ください。