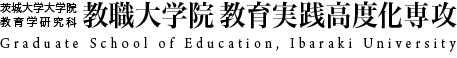過去のお知らせ
年度毎のインデックス
お知らせ
-
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科入学試験(2次募集)合格者発表について
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科入学試験(2次募集)合格者発表について掲載しました。
[こちら]をご覧ください。 -
第9回教育実践フォーラムの開催について
茨城大学教職大学院では、第9回教育実践フォーラムを以下のとおり開催します。
日時:2026年2月28日(土)10:00~17:30(オンライン開場 9:30~)
場所:対面(教育学部D棟2階D201教室)オンライン(Microsoft Teamsによるオンライン会議)併用
参加申込締切:2026年2月16日(月)まで申込はこちら
-
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項(2次募集)の公表について
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項(2次募集)を
公表いたしました。出願期間:令和8年1月7日(水)~1月16日(金)
試 験 日:令和8年2月14日(土)募集要項はこちらからご確認いただけます。
【問い合わせ先】
学部等支援部水戸地区事務課教育学部学務グループ
TEL:029-228-8203 -
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科入学試験合格者発表について
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科入学試験合格者発表について掲載しました。
[こちら]をご覧ください。 -
「教材開発実習(美術館)」の「対話型アートツアー」の準備
教科領域・特別支援科学コースの1・2年生24名が、茨城県近代美術館において
「教材開発実習ⅠB」「教材開発実習ⅡB」を実施しました。
小学生を対象とした『アートツアー』の実践に向けて、2日目の9/12には県内の小学校団体様来館の様子を見学させていただきました。その後、美術館の職員の皆様にご指導をいただき、演習、省察を繰り返しました。
11月には、県内小学校団体様をお迎えし、「ART鑑賞トランク」を使用した対話型鑑賞のファシリテーターを務めさせていただきます。


-
第2回茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院:専門職学位課程)入試説明会【オンライン開催】のお知らせ
第2回茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院:専門職学位課程)の入試説明会を以下のとおり開催いたします。
教職大学院に興味のある方は、ぜひご参加ください。
内容は7月26日(土)開催の第1回入試説明会と同様です。日 時:2025年9月20日(土) 13:00 ~ 14:00
開催方法:オンライン(Zoom)
主な内容:大学院概要説明、大学院入試説明、質疑応答【参加方法】
こちらまたは以下のPDFファイルに記載のQRコードより、9月17日(水)17:00までにお申し込みください。 -
大学院入試説明会を実施しました
令和8(2026)年度教職大学院入試説明会を、7月26日(土)にオンラインも併用したハイブリッドで開催しました。
全体説明会とコース別説明会のあとに、過去の入試問題を説明会会場で閲覧してもらいました。
学内外から多数の出席者があり、各説明会でも活発な質疑応答がありました。




-
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項における宛名票について
2025年6月24日に公表した令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項について、所定用紙に宛名票の様式が抜けていたため、追加したものに更新しました。
募集要項はこちらからご確認いただけます。
すでに学生募集要項をダウンロード済みの方は、お手数ですが再度ダウンロードください。
【問い合わせ先】
学部等支援部水戸地区事務課教育学部学務グループ
TEL:029-228-8203 -
第8回教育実践フォーラムを開催しました
教育実践フォーラムが3月1日(土)に開催されました。全体会では、「GIGAスクール構想の実現に向けた学校教育の取り組み~つくば市の取り組みと令和の日本型学校教育」と題して、森田充氏(つくば市教育長)にご講演いただきました。
全体会に続いて開催されたコースごとの分科会では、6コースの院生による研究成果が発表されました。
分科会終了後には、第2回ホームカミングデイ(懇親会)を茨苑会館ベーカリーにて開催いたしました。【懇親会】
4rev-169x300.jpeg)
6-rev-187x300.jpeg)
1-300x225.jpeg)
-
課題発見実習報告会のご案内
学校運営コース、教育方法開発コース、児童生徒支援コースの3コースでは、4~6月にかけて附属学校園における課題発見実習を実施しております。
その成果と課題について、報告会(オンライン)を開催する運びとなりましたので、 ご案内申し上げます。興味・関心のある学生・院生・教員の方は、この機会にぜひ、お申し込みください。
なお、誠に勝手ながら、一般の方は参加することはできませんので、ご了承ください。
-
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項の公表について
令和8年度茨城大学大学院教育学研究科(教職大学院)学生募集要項を
公表いたしました。出願期間:令和7年9月29日(月)~10月10日(金)
試 験 日:令和7年11月1日(土)募集要項はこちらからご確認いただけます。
詳細については、以下の問い合わせ先までお気軽にお問い合わせください。
【問い合わせ先】
学部等支援部水戸地区事務課教育学部学務グループ
TEL:029-228-8203 -
茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院:専門職学位課程)入試説明会【対面・オンライン同時開催】のお知らせ
茨城大学大学院教育学研究科教育実践高度化専攻(教職大学院:専門職学位課程)の入試説明会を以下のとおり開催いたします。 教職大学院に興味のある方は、ぜひご参加ください。
日時 2025年7月26日(土) 13:00 ~ 15:00
開催方法:対面(茨城大学教育学部D棟201教室)
またはオンライン(Zoom)でも参加可能です。
主な内容:研究科長挨拶、大学院概要説明、コース別説明会、個別相談会(第1・第2希望)、大学院入試説【参加方法】
こちらまたは以下のPDFファイルに記載のQRコードより、7月18日(金)までにお申し込みください。